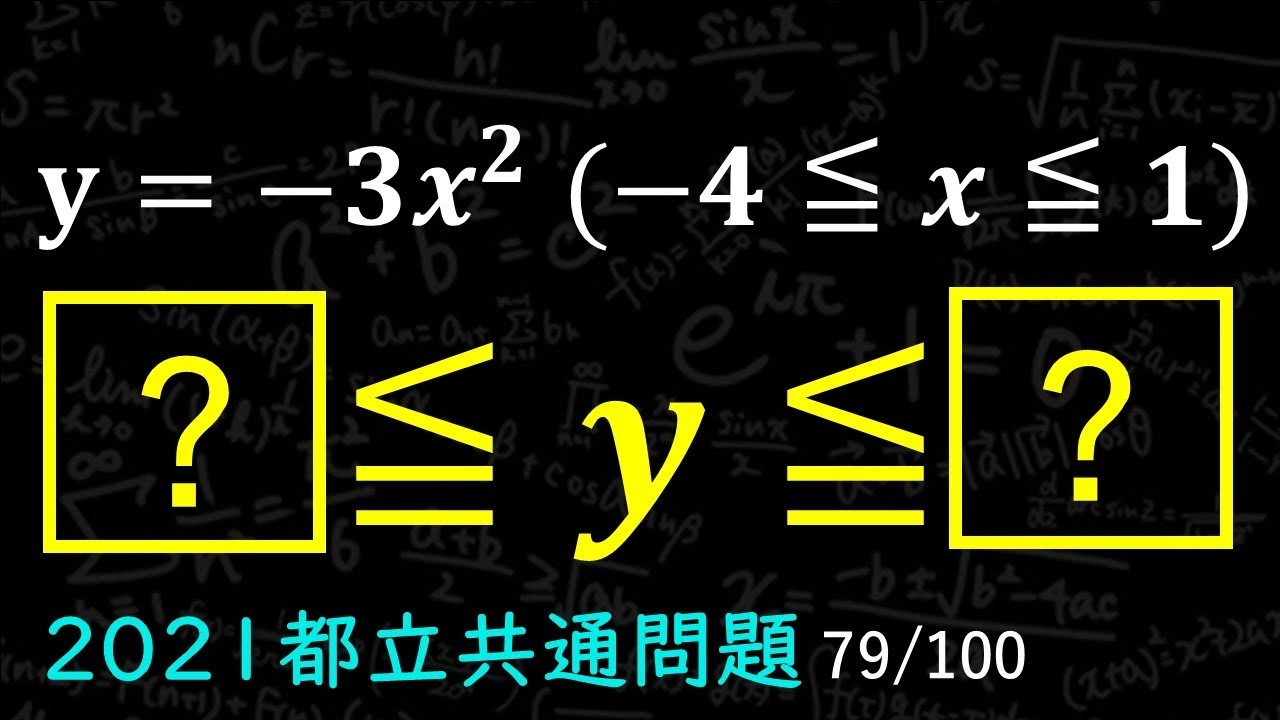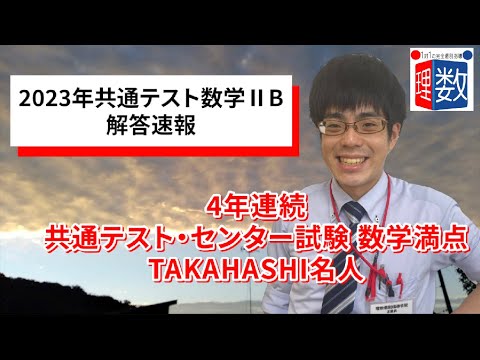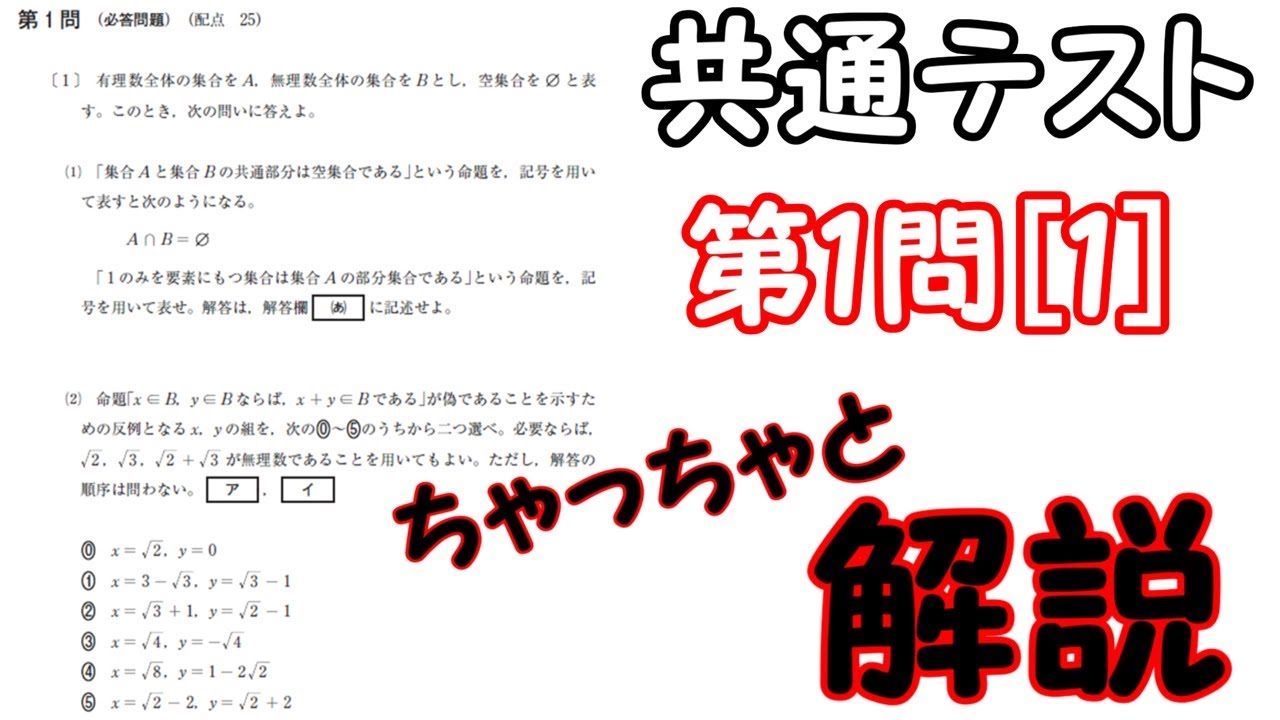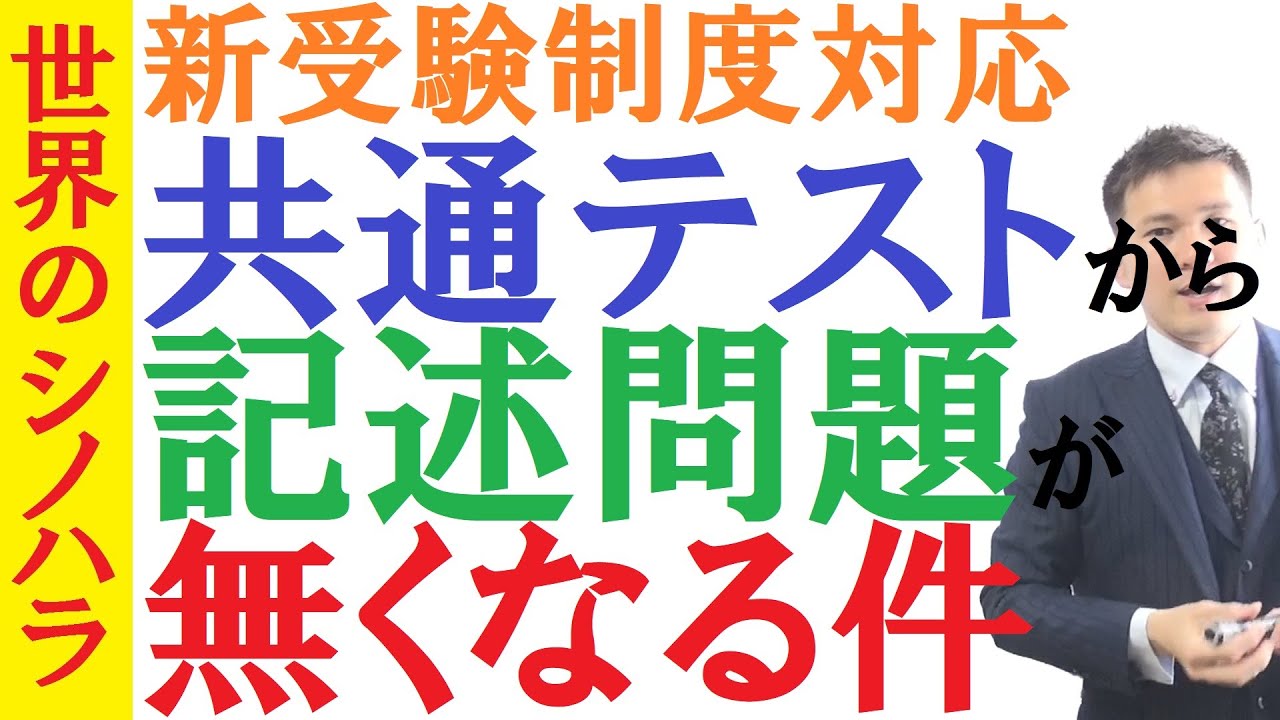問題文全文(内容文):
共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です
共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です
単元:
#大学入試過去問(数学)#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)
指導講師:
【楽しい授業動画】あきとんとん
問題文全文(内容文):
共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です
共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です
投稿日:2019.09.22