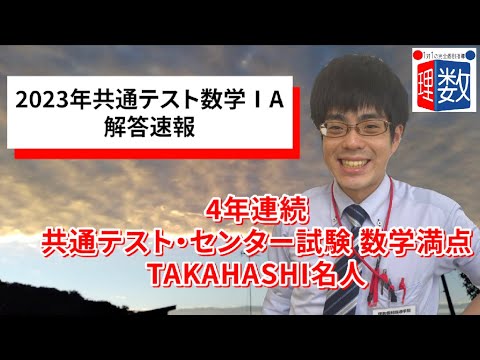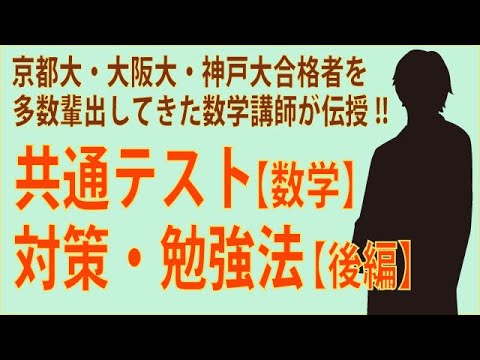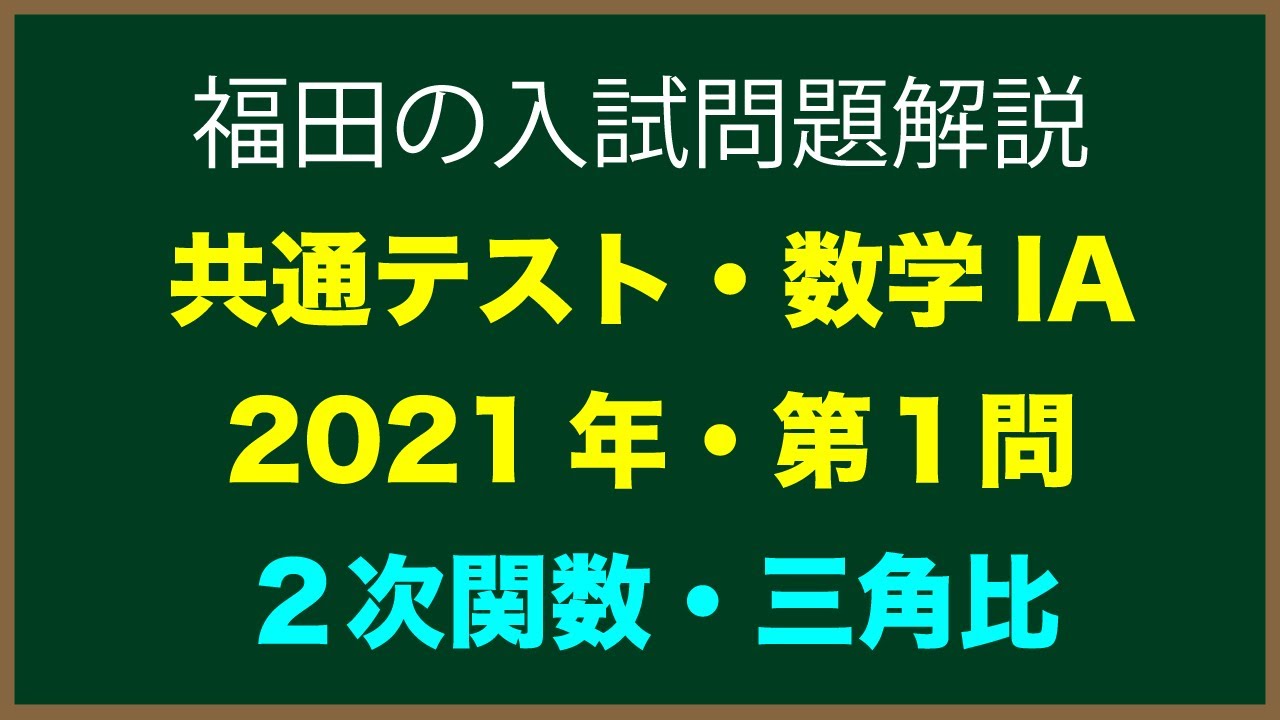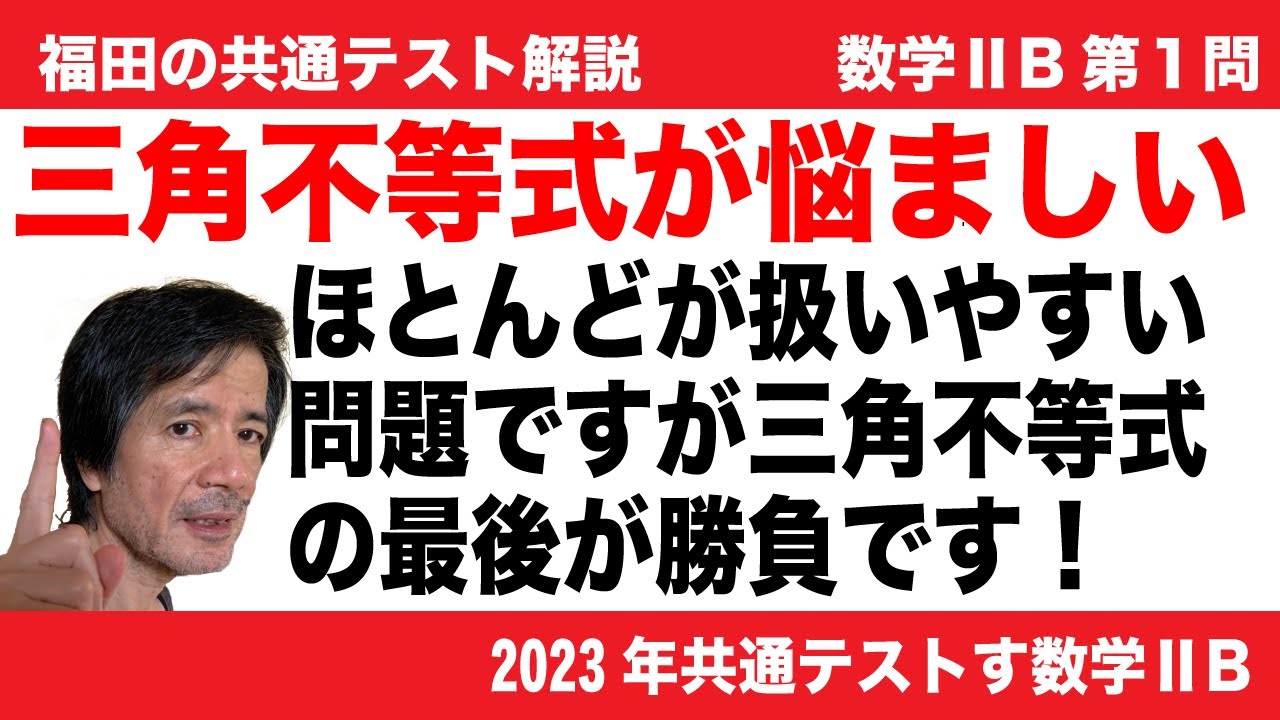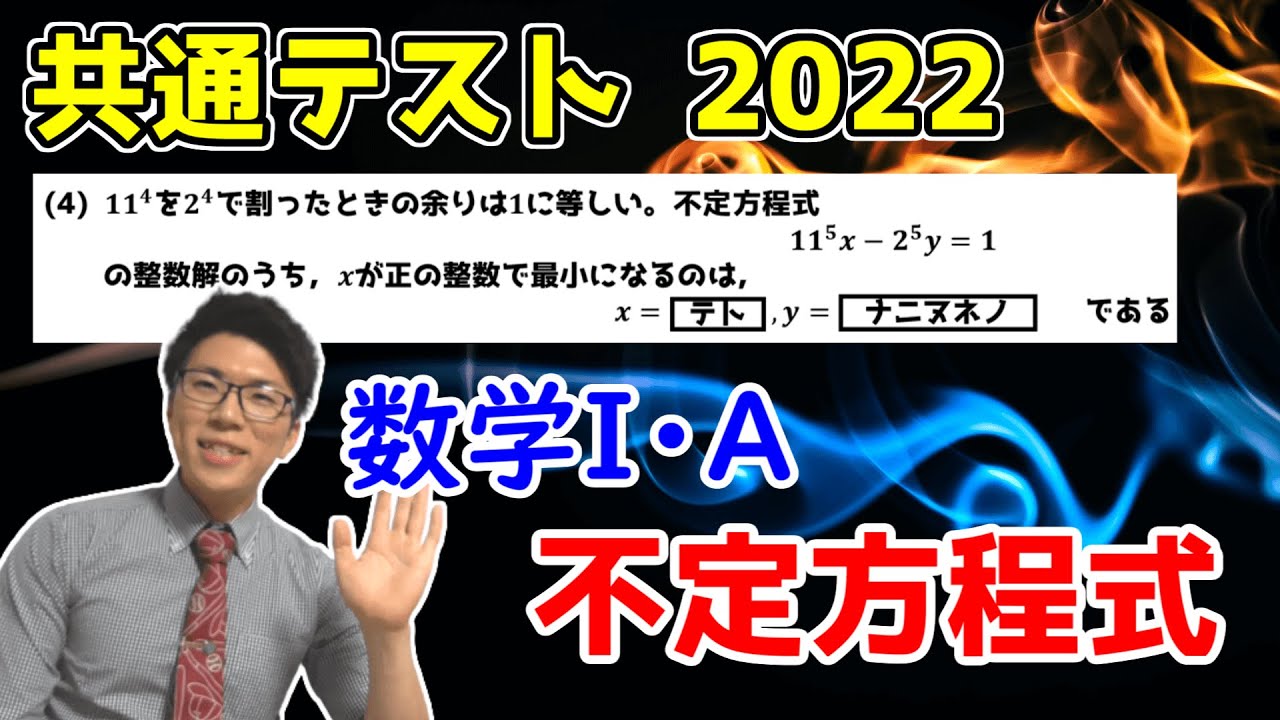単元:
#数Ⅰ#大学入試過去問(数学)#図形と計量#三角比(三角比・拡張・相互関係・単位円)#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)
指導講師:
福田次郎
問題文全文(内容文):
${\large第1問}$
[1]$c$を正の整数とする。$x$の2次方程式
$2x^2+(4c-3)x+2c^2$$-c-11=0$ $\cdots$①
について考える。
(1)$c=1$のとき、①のっ左辺を因数分解すると
$\left(\boxed{\ \ ア\ \ }\ x+\boxed{\ \ イ\ \ }\right)\left(x-\boxed{\ \ ウ\ \ }\right)$
であるから、①の解は
$x=-\displaystyle \frac{\boxed{\ \ イ\ \ }}{\boxed{\ \ ア\ \ }},\ \boxed{\ \ ウ\ \ }$
である。
(2)$c=2$のとき、①の解は
$x=\displaystyle \frac{-\boxed{\ \ エ\ \ }\pm\sqrt{\boxed{\ \ オカ\ \ }}}{\boxed{\ \ キ\ \ }}$
であり、大きい方の解を$\alpha$とすると
$\displaystyle \frac{5}{\alpha}=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ク\ \ }\pm\sqrt{\boxed{\ \ ケコ\ \ }}}{\boxed{\ \ サ\ \ }}$
である。また、$m \lt \displaystyle \frac{5}{\alpha} \lt m+1$を満たす整数$m$は$\boxed{\ \ シ\ \ }$である。
(3)太郎さんと花子さんは、①の解について考察している。
太郎:①の解は$c$の値によって、ともに有理数である場合も
あれば、ともに無理数である場合もあるね。$c$がどの
ような値のときに、解は有理数になるのかな。
花子:2次方程式の解の公式の根号の中に着目すれば
いいんじゃないかな。
①の解が異なる二つの有理数であるような正の整数$c$の個数は
$\boxed{\ \ ス\ \ }$個である。
[2]右の図のように(※動画参照)、$\triangle ABC$の外側に辺$AB,BC,CA$
をそれぞれ1辺とする正方形$ADEB,BFGC,CHIA$をかき、
2点$E$と$F,G$と$H,I$と$D$をそれぞれ線分で結んだ図形を考える。
以下において
$BC=a, CA=b, AB=c$
$\angle CAB=A, \angle ABC=B, $$\angle BCA=C$
とする。
(1)$b=6,c=5,\cos A=\displaystyle \frac{3}{5}$のとき、$\sin A=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ セ\ \ }}{\boxed{\ \ ソ\ \ }}$であり、
$\triangle ABC$の面積は$\boxed{\ \ タチ\ \ }、\triangle AID$の面積は$\boxed{\ \ ツテ\ \ }$である。
(2)正方形$BFGC, CHIA, ADEB$の面積をそれぞれ$S_1,S_2,S_3$とする。
このとき、$S_1-S_2-S_3$は
・$0° \lt A \lt 90°$のとき、$\boxed{\boxed{\ \ ト\ \ }}$。
・$A=90°$のとき、$\boxed{\boxed{\ \ ナ\ \ }}$。
・$90° \lt A \lt 180°$のとき、$\boxed{\boxed{\ \ ニ\ \ }}$。
$\boxed{\boxed{\ \ ト\ \ }}~\boxed{\boxed{\ \ ニ\ \ }}$の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)
⓪$0$である
①正の値である
②負の値である
③正の値も負の値もとる
(3)$\triangle AID,\triangle BEF,\triangle CGH$の面積をそれぞれ$T_1,T_2,T_3$とする。
このとき、$\boxed{\boxed{\ \ ヌ\ \ }}$である。
$\boxed{\boxed{\ \ ヌ\ \ }}$の解答群
⓪$a \lt b \lt c$ならば、$T_1 \gt T_2 \gt T_3$
①$a \lt b \lt c$ならば、$T_1 \lt T_2 \lt T_3$
②$A$が鈍角ならば、$T_1 \lt T_2かつT_2 \lt T_3$
③$a,b,c$の値に関係なく、$T_1=T_2=T_3$
(4)$\triangle ABC,\triangle AID,\triangle BEF,\triangle CGH$のうち、外接円の半径が最も小さい
ものを求める。
$0° \lt A \lt 90°$のとき、$ID \boxed{\boxed{\ \ ネ\ \ }}BC$であり
($\triangle AID$の外接円の半径)$\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$($\triangle ABC$の外接円の半径)
であるから、外接円の半径が最も小さい三角形は
・$0° \lt A \lt B \lt C \lt 90°$のとき、$\boxed{\boxed{\ \ ハ\ \ }}$である。
・$0° \lt A \lt B \lt 90° \lt $Cのとき、$\boxed{\boxed{\ \ ヒ\ \ }}$である。
$\boxed{\boxed{\ \ ネ\ \ }},\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)
⓪$\lt$ ①$=$ ②$\gt$
$\boxed{\boxed{\ \ ハ\ \ }},\boxed{\boxed{\ \ ヒ\ \ }}$の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)
⓪$\triangle ABC$ ①$\triangle AID$ ②$\triangle BEF$ ③$\triangle CGH$
2021共通テスト過去問
この動画を見る