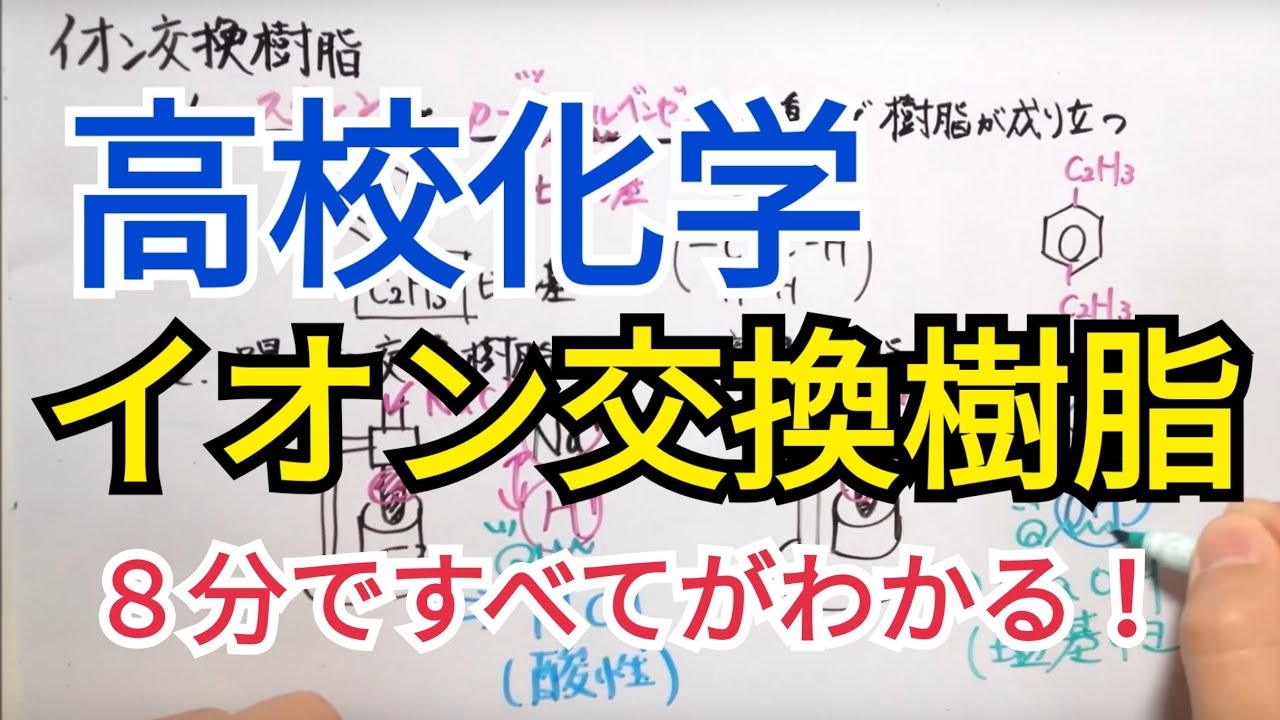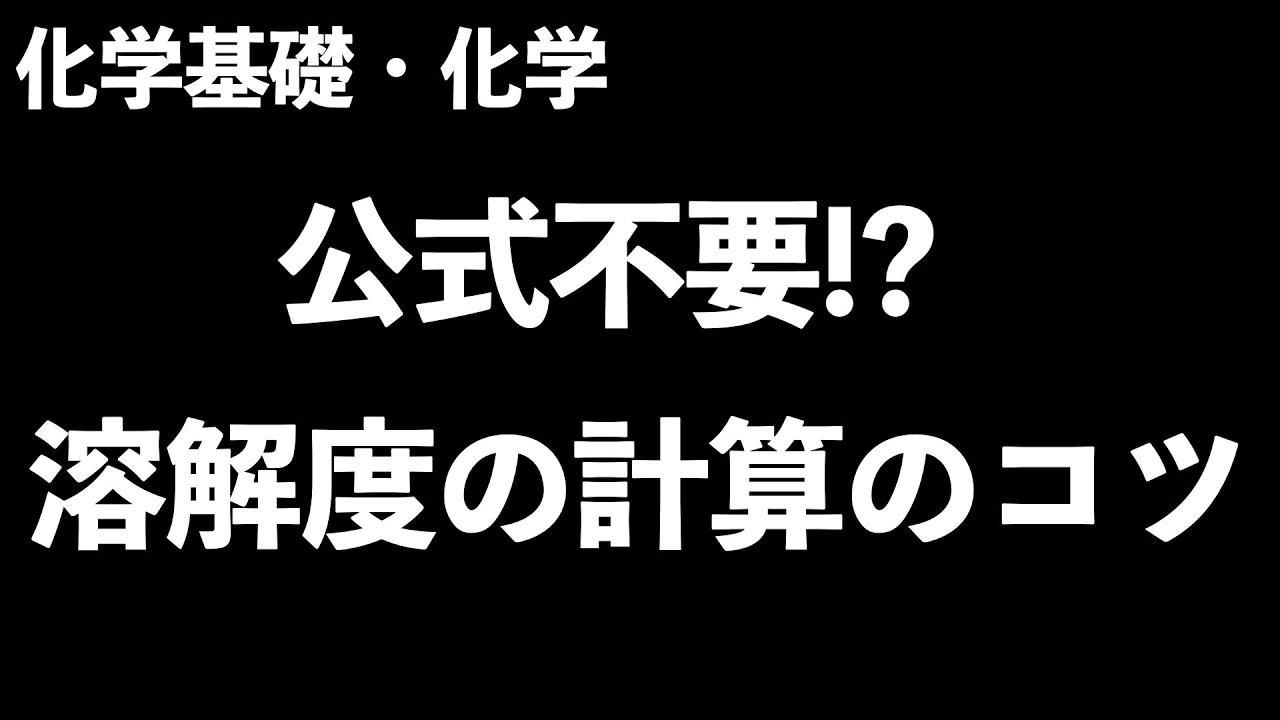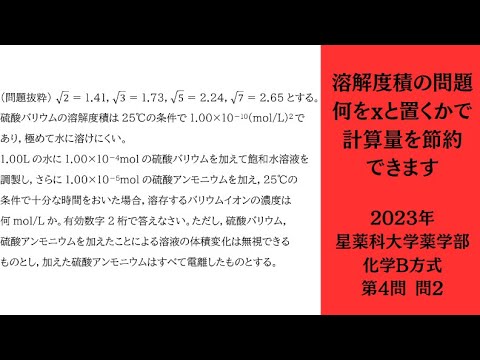問題文全文(内容文):
【問題1】
ある濃度の硫酸20mLを中和するのに、0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が
10mL必要であった。硫酸の濃度はいくつか。
【問題2】
濃度不明の硫酸10.0mLを0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定したが、
中和点をこえて12.5ml滴下してしまった。
そこで0.010mol/Lの塩酸で再び中和滴定したところ、5.0ml中和点となった。
硫酸の濃度は?
【問題1】
ある濃度の硫酸20mLを中和するのに、0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が
10mL必要であった。硫酸の濃度はいくつか。
【問題2】
濃度不明の硫酸10.0mLを0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定したが、
中和点をこえて12.5ml滴下してしまった。
そこで0.010mol/Lの塩酸で再び中和滴定したところ、5.0ml中和点となった。
硫酸の濃度は?
単元:
#化学#化学基礎2ー物質の変化#中和と塩#理科(高校生)
指導講師:
受験メモ山本
問題文全文(内容文):
【問題1】
ある濃度の硫酸20mLを中和するのに、0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が
10mL必要であった。硫酸の濃度はいくつか。
【問題2】
濃度不明の硫酸10.0mLを0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定したが、
中和点をこえて12.5ml滴下してしまった。
そこで0.010mol/Lの塩酸で再び中和滴定したところ、5.0ml中和点となった。
硫酸の濃度は?
【問題1】
ある濃度の硫酸20mLを中和するのに、0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が
10mL必要であった。硫酸の濃度はいくつか。
【問題2】
濃度不明の硫酸10.0mLを0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定したが、
中和点をこえて12.5ml滴下してしまった。
そこで0.010mol/Lの塩酸で再び中和滴定したところ、5.0ml中和点となった。
硫酸の濃度は?
投稿日:2019.07.06