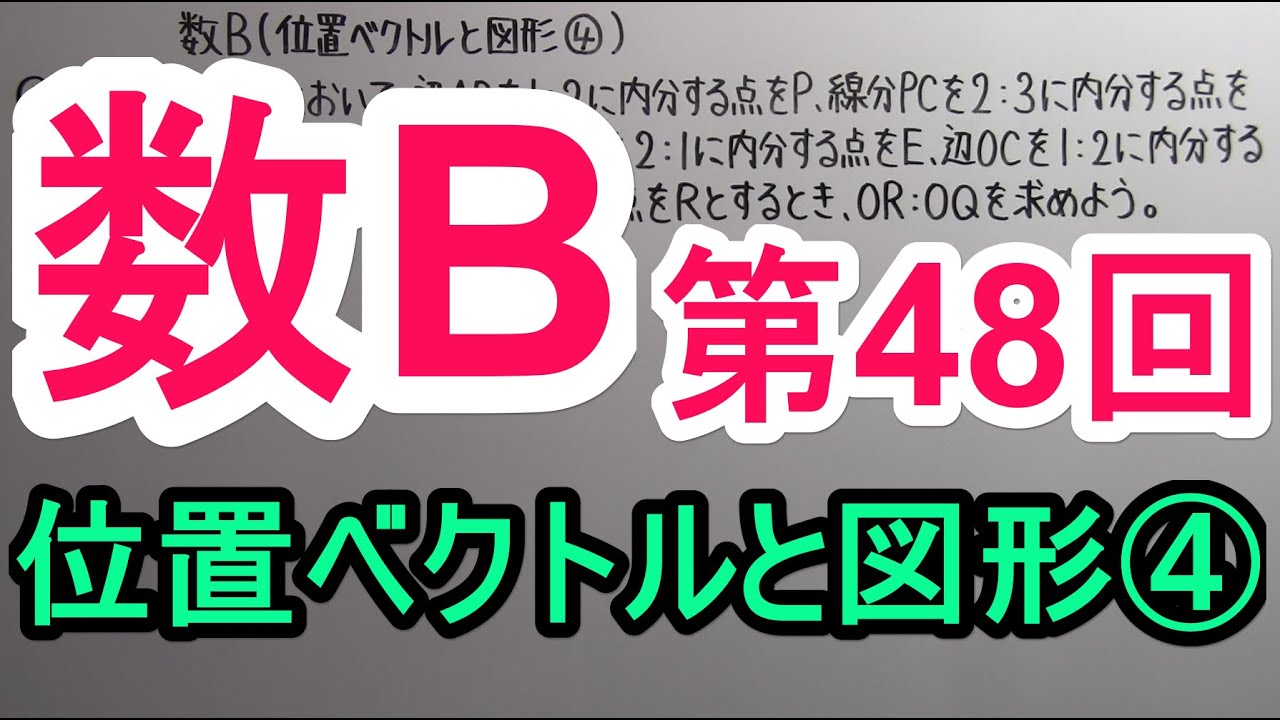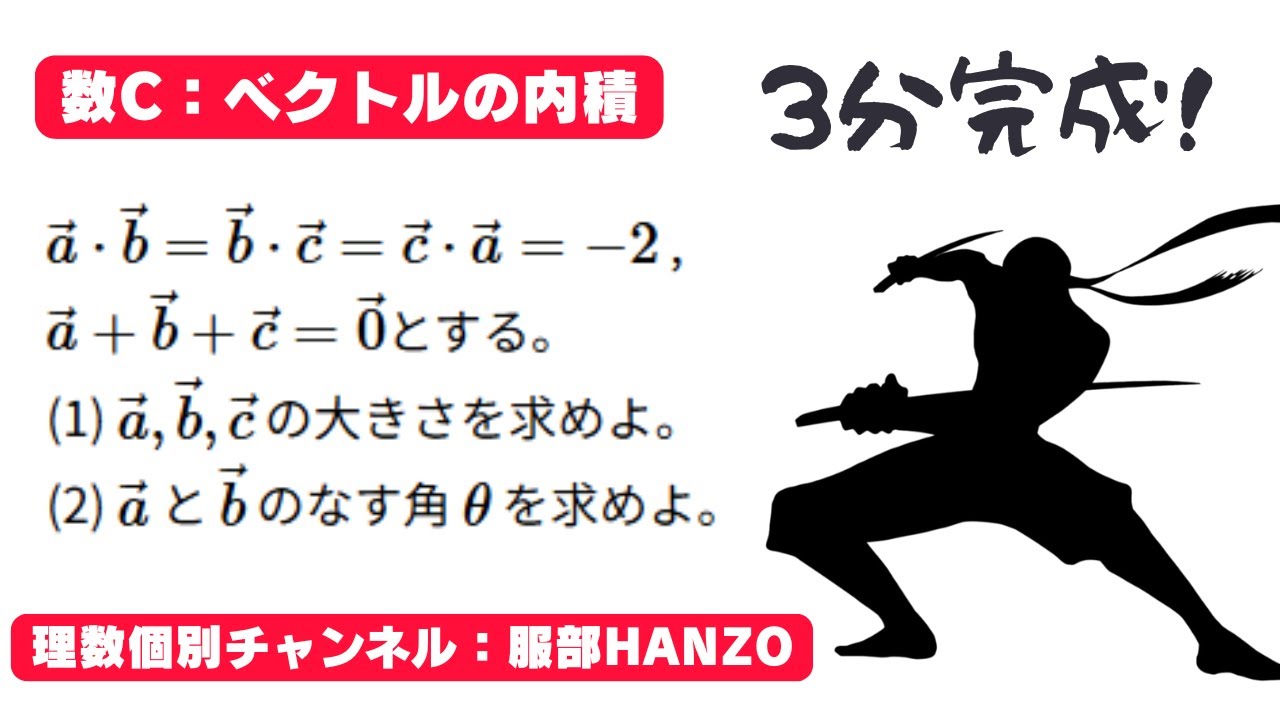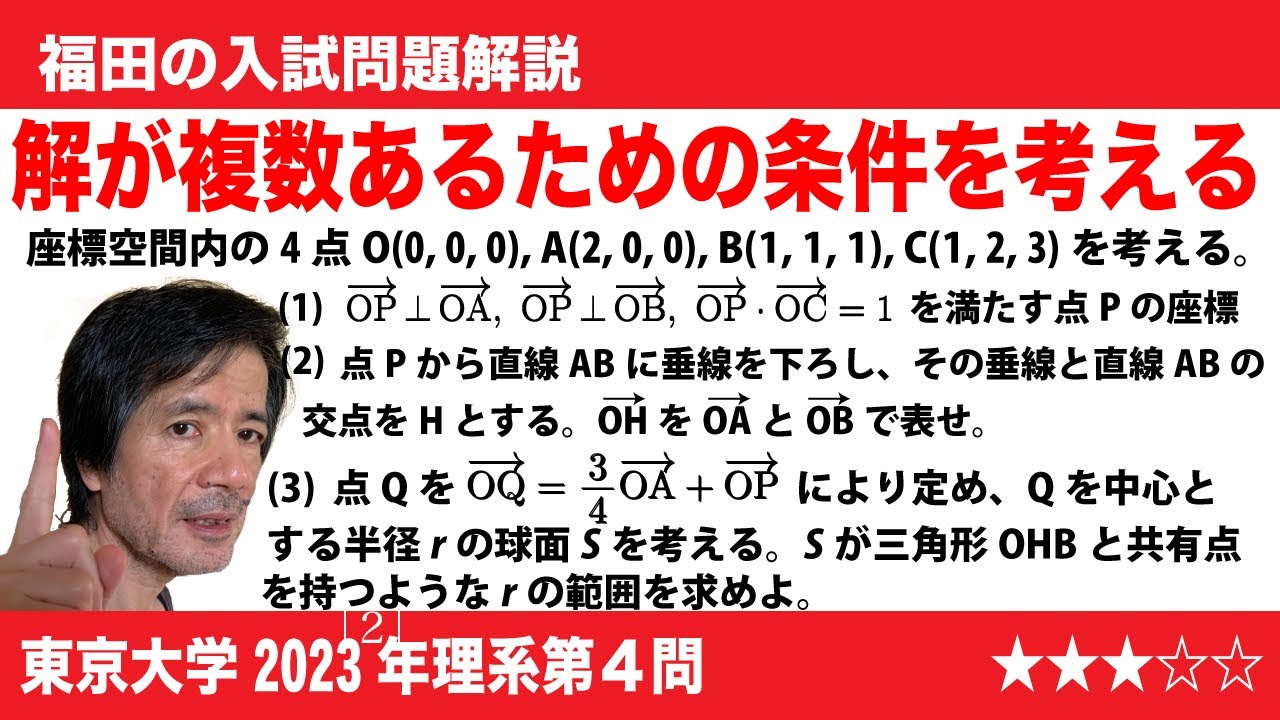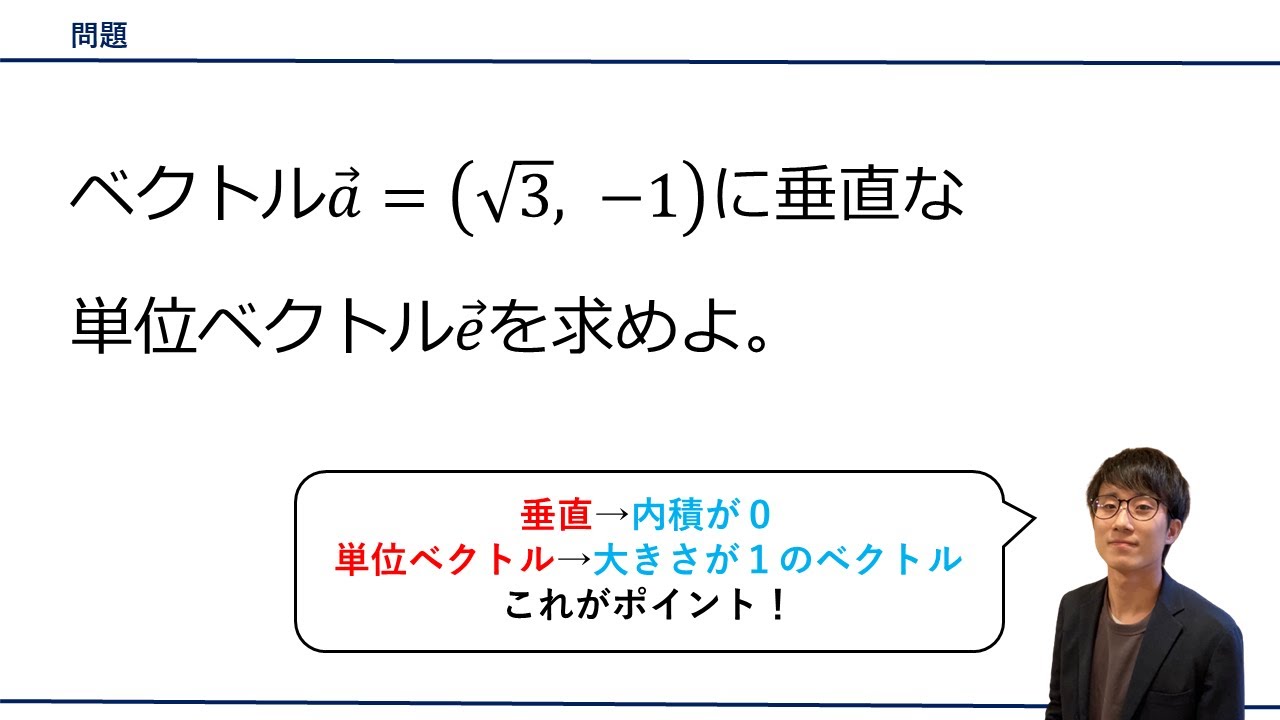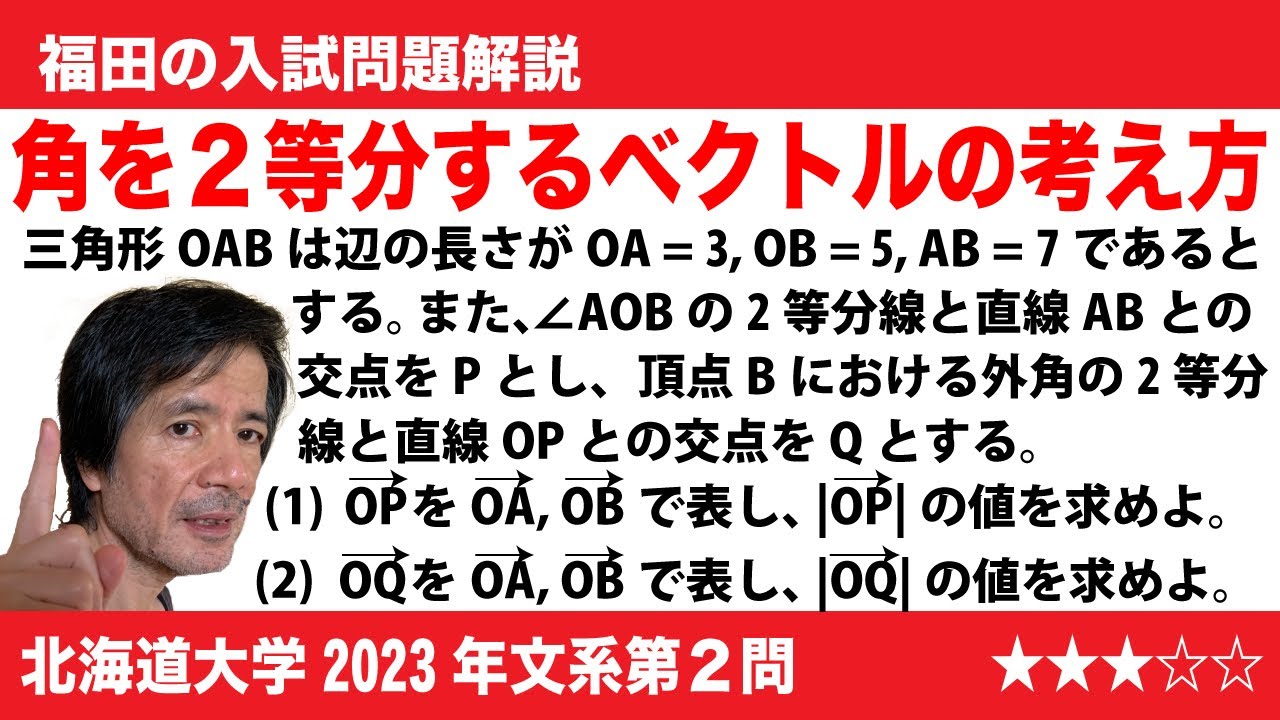問題文全文(内容文):
平行四辺形ABCDにおいて、2辺AB,ADの中点をそれぞれE,Fとし、線分BFと線分CEの交点をGとする。AB=B,AD=dとするとき、次の問に答えよ。
(1)AGをbとdを用いて表せ。
(2)AGの延長と辺BCの交点をHとする。このとき、Hは辺BCをどのような比に内分するか。
平行四辺形ABCDにおいて、2辺AB,ADの中点をそれぞれE,Fとし、線分BFと線分CEの交点をGとする。AB=B,AD=dとするとき、次の問に答えよ。
(1)AGをbとdを用いて表せ。
(2)AGの延長と辺BCの交点をHとする。このとき、Hは辺BCをどのような比に内分するか。
チャプター:
0:00 オープニング
0:05 問題文
0:15 問題解説(1):sとtの2通りで表す
3:25 問題文
3:31 問題解説(2):一直線はk倍、内分点は係数和が1
6:08 別解:メネチェバの利用
7:02 名言
単元:
#平面上のベクトル#ベクトルと平面図形、ベクトル方程式#数学(高校生)#数C
指導講師:
理数個別チャンネル
問題文全文(内容文):
平行四辺形ABCDにおいて、2辺AB,ADの中点をそれぞれE,Fとし、線分BFと線分CEの交点をGとする。AB=B,AD=dとするとき、次の問に答えよ。
(1)AGをbとdを用いて表せ。
(2)AGの延長と辺BCの交点をHとする。このとき、Hは辺BCをどのような比に内分するか。
平行四辺形ABCDにおいて、2辺AB,ADの中点をそれぞれE,Fとし、線分BFと線分CEの交点をGとする。AB=B,AD=dとするとき、次の問に答えよ。
(1)AGをbとdを用いて表せ。
(2)AGの延長と辺BCの交点をHとする。このとき、Hは辺BCをどのような比に内分するか。
投稿日:2020.09.15