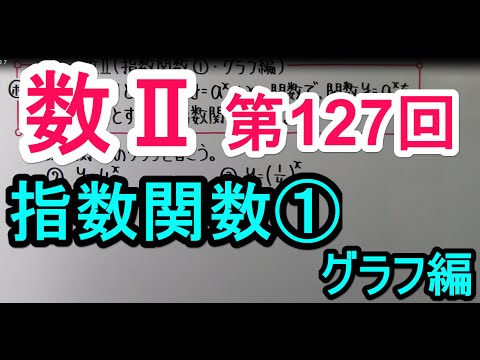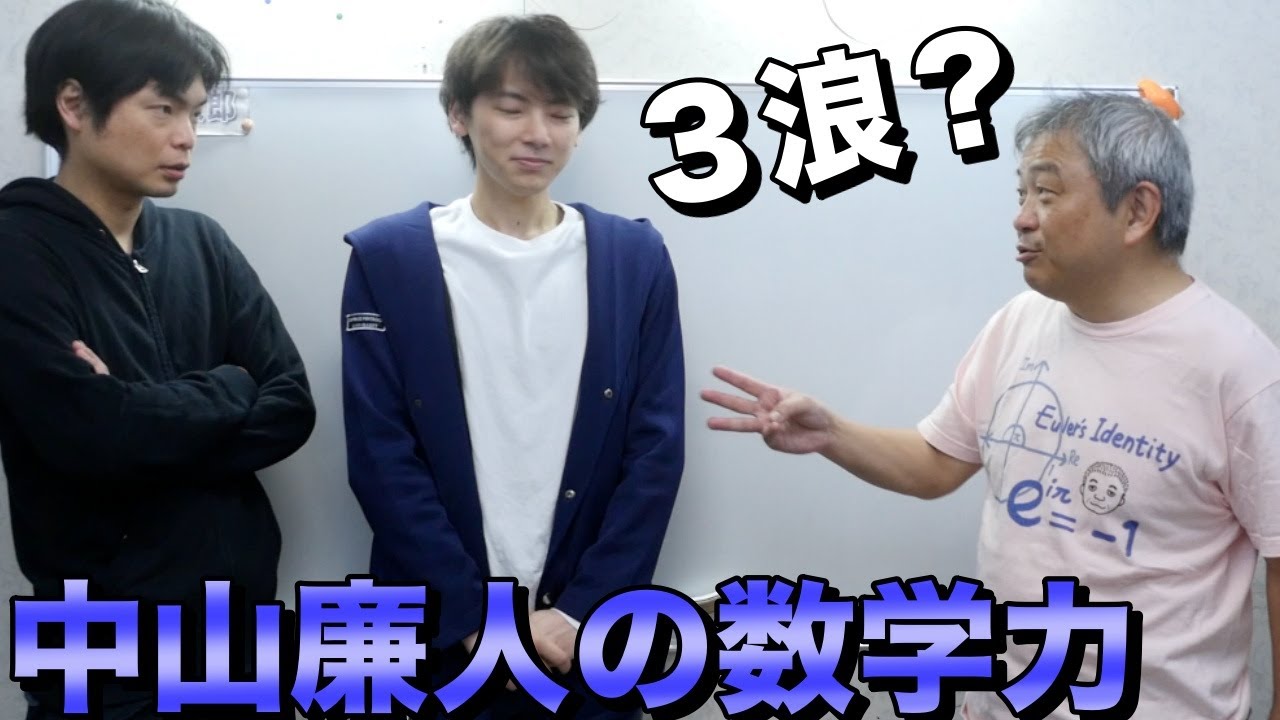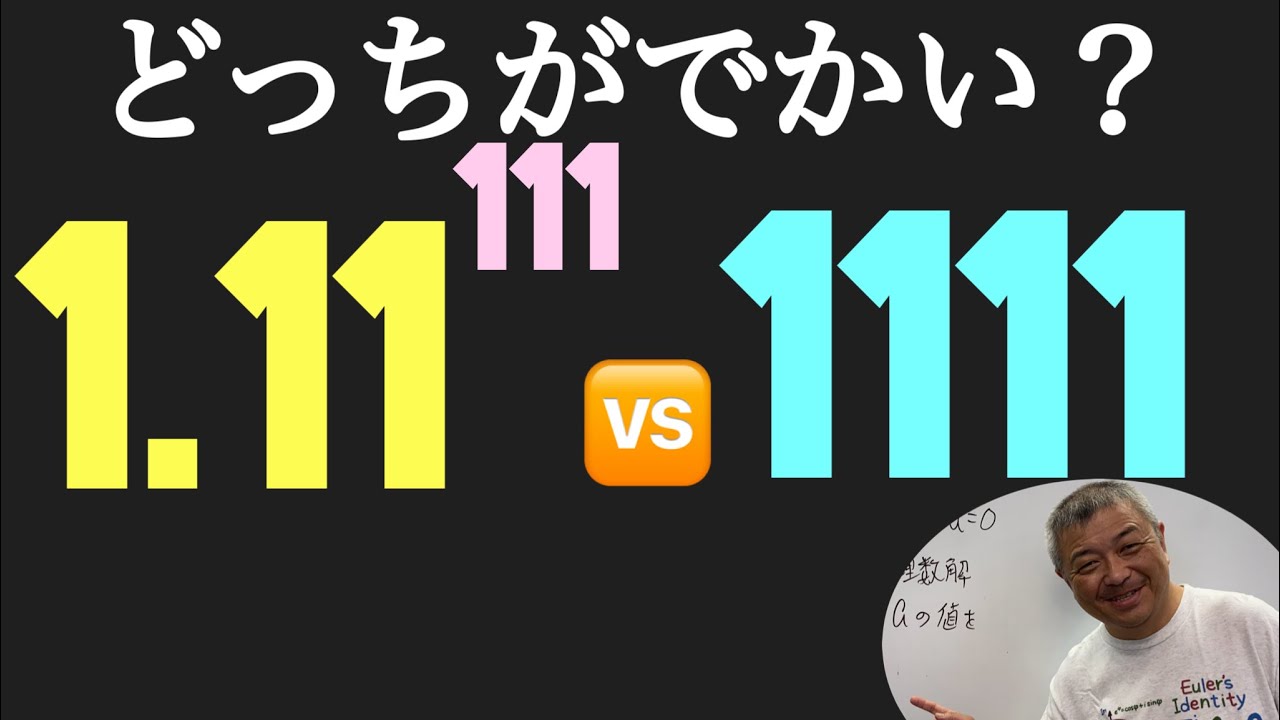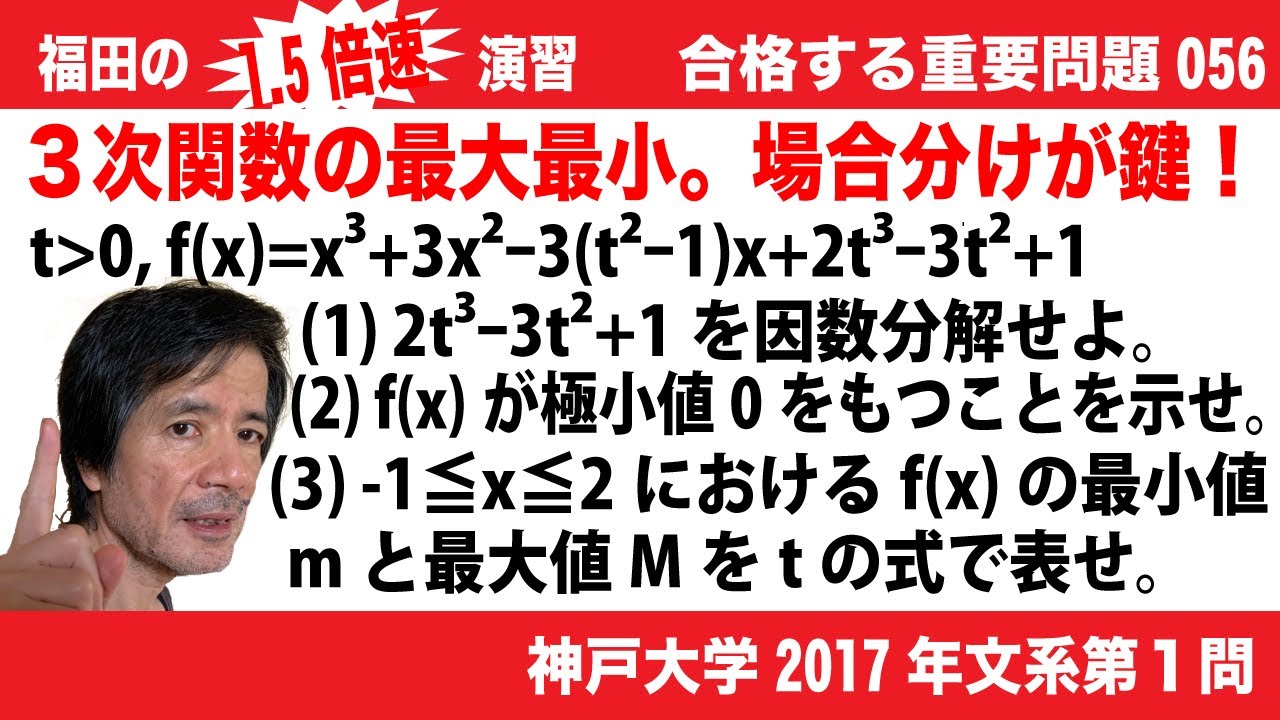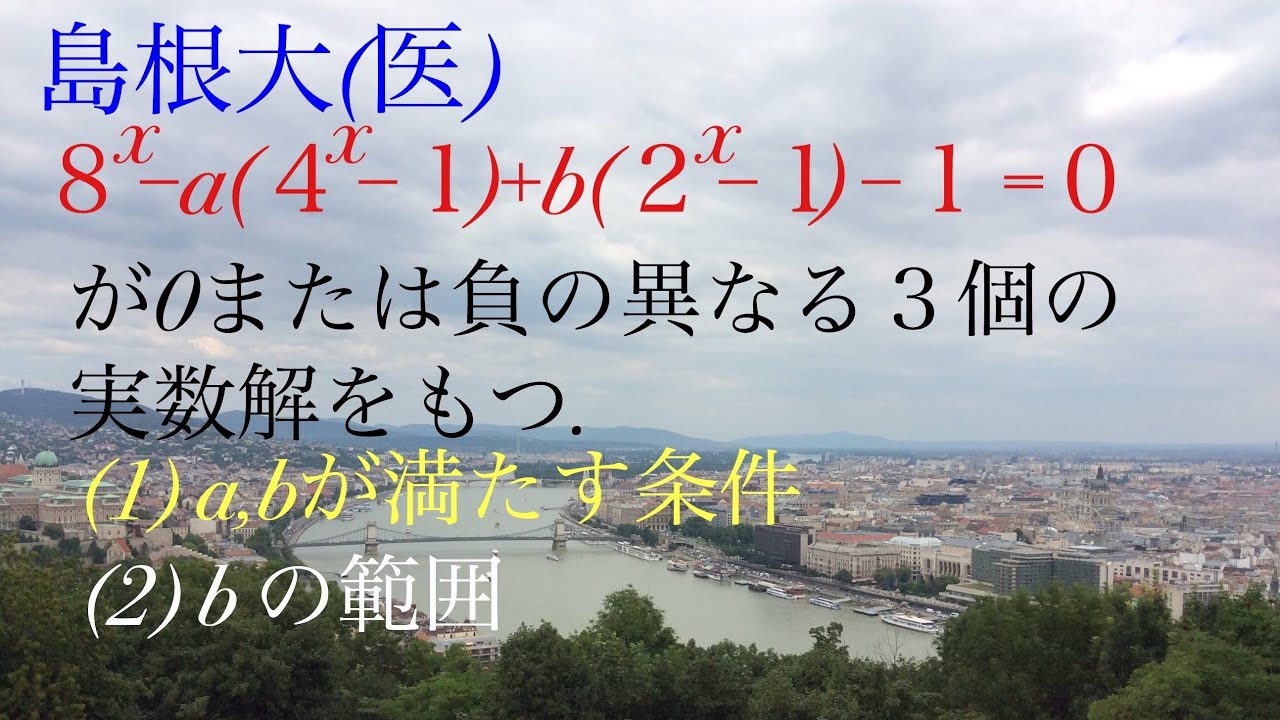問題文全文(内容文):
${\Large\boxed{2}}$(2)座標平面上で、次の3つの3次関数のグラフについて考える。$y=4x^3+2x^2+3x+5 \ldots④ y=-2x^3+7x^2+3x+5 \ldots⑤$
$y=5x^3-x^2+3x+5 \ldots⑥$
④,⑤,⑥の3次関数のグラフには次の共通点がある。
共通点:・y軸との交点のy座標は$\boxed{ソ}$である。
・y軸との交点における接線の方程式は $y=\boxed{タ}\ x+\boxed{チ}$ である。
$a,b,c,d$を0でない実数とする。
曲線$y=ax^3+bx^2+cx+d$上の点$(0, \boxed{ツ})$における接線の方程式は
$y=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$ である。
次に$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d, g(x)=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$とし、
$f(x)-g(x)$について考える。
$h(x)=f(x)-g(x)$とおく。a,b,c,dが正の実数であるとき、$y=h(x)$のグラフ
の概形は$\boxed{ナ}$である。
(※$\boxed{ナ}$の解答群は動画参照)
$y=f(x)$のグラフと$y=g(x)$のグラフの共有点のx座標は$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$である。
また、xが$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$の間を動くとき、
$|f(x)-g(x)|$の値が最大となるのは、$x=\frac{\boxed{ハヒフ}}{\boxed{ヘホ}}$のときである。
2021共通テスト数学過去問
${\Large\boxed{2}}$(2)座標平面上で、次の3つの3次関数のグラフについて考える。$y=4x^3+2x^2+3x+5 \ldots④ y=-2x^3+7x^2+3x+5 \ldots⑤$
$y=5x^3-x^2+3x+5 \ldots⑥$
④,⑤,⑥の3次関数のグラフには次の共通点がある。
共通点:・y軸との交点のy座標は$\boxed{ソ}$である。
・y軸との交点における接線の方程式は $y=\boxed{タ}\ x+\boxed{チ}$ である。
$a,b,c,d$を0でない実数とする。
曲線$y=ax^3+bx^2+cx+d$上の点$(0, \boxed{ツ})$における接線の方程式は
$y=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$ である。
次に$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d, g(x)=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$とし、
$f(x)-g(x)$について考える。
$h(x)=f(x)-g(x)$とおく。a,b,c,dが正の実数であるとき、$y=h(x)$のグラフ
の概形は$\boxed{ナ}$である。
(※$\boxed{ナ}$の解答群は動画参照)
$y=f(x)$のグラフと$y=g(x)$のグラフの共有点のx座標は$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$である。
また、xが$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$の間を動くとき、
$|f(x)-g(x)|$の値が最大となるのは、$x=\frac{\boxed{ハヒフ}}{\boxed{ヘホ}}$のときである。
2021共通テスト数学過去問
単元:
#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#指数関数と対数関数#微分法と積分法#指数関数#接線と増減表・最大値・最小値#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)
指導講師:
福田次郎
問題文全文(内容文):
${\Large\boxed{2}}$(2)座標平面上で、次の3つの3次関数のグラフについて考える。$y=4x^3+2x^2+3x+5 \ldots④ y=-2x^3+7x^2+3x+5 \ldots⑤$
$y=5x^3-x^2+3x+5 \ldots⑥$
④,⑤,⑥の3次関数のグラフには次の共通点がある。
共通点:・y軸との交点のy座標は$\boxed{ソ}$である。
・y軸との交点における接線の方程式は $y=\boxed{タ}\ x+\boxed{チ}$ である。
$a,b,c,d$を0でない実数とする。
曲線$y=ax^3+bx^2+cx+d$上の点$(0, \boxed{ツ})$における接線の方程式は
$y=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$ である。
次に$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d, g(x)=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$とし、
$f(x)-g(x)$について考える。
$h(x)=f(x)-g(x)$とおく。a,b,c,dが正の実数であるとき、$y=h(x)$のグラフ
の概形は$\boxed{ナ}$である。
(※$\boxed{ナ}$の解答群は動画参照)
$y=f(x)$のグラフと$y=g(x)$のグラフの共有点のx座標は$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$である。
また、xが$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$の間を動くとき、
$|f(x)-g(x)|$の値が最大となるのは、$x=\frac{\boxed{ハヒフ}}{\boxed{ヘホ}}$のときである。
2021共通テスト数学過去問
${\Large\boxed{2}}$(2)座標平面上で、次の3つの3次関数のグラフについて考える。$y=4x^3+2x^2+3x+5 \ldots④ y=-2x^3+7x^2+3x+5 \ldots⑤$
$y=5x^3-x^2+3x+5 \ldots⑥$
④,⑤,⑥の3次関数のグラフには次の共通点がある。
共通点:・y軸との交点のy座標は$\boxed{ソ}$である。
・y軸との交点における接線の方程式は $y=\boxed{タ}\ x+\boxed{チ}$ である。
$a,b,c,d$を0でない実数とする。
曲線$y=ax^3+bx^2+cx+d$上の点$(0, \boxed{ツ})$における接線の方程式は
$y=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$ である。
次に$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d, g(x)=\boxed{テ}\ x+\boxed{ト}$とし、
$f(x)-g(x)$について考える。
$h(x)=f(x)-g(x)$とおく。a,b,c,dが正の実数であるとき、$y=h(x)$のグラフ
の概形は$\boxed{ナ}$である。
(※$\boxed{ナ}$の解答群は動画参照)
$y=f(x)$のグラフと$y=g(x)$のグラフの共有点のx座標は$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$である。
また、xが$\frac{\boxed{ニヌ}}{\boxed{ネ}}$と$\boxed{ノ}$の間を動くとき、
$|f(x)-g(x)|$の値が最大となるのは、$x=\frac{\boxed{ハヒフ}}{\boxed{ヘホ}}$のときである。
2021共通テスト数学過去問
投稿日:2022.01.13