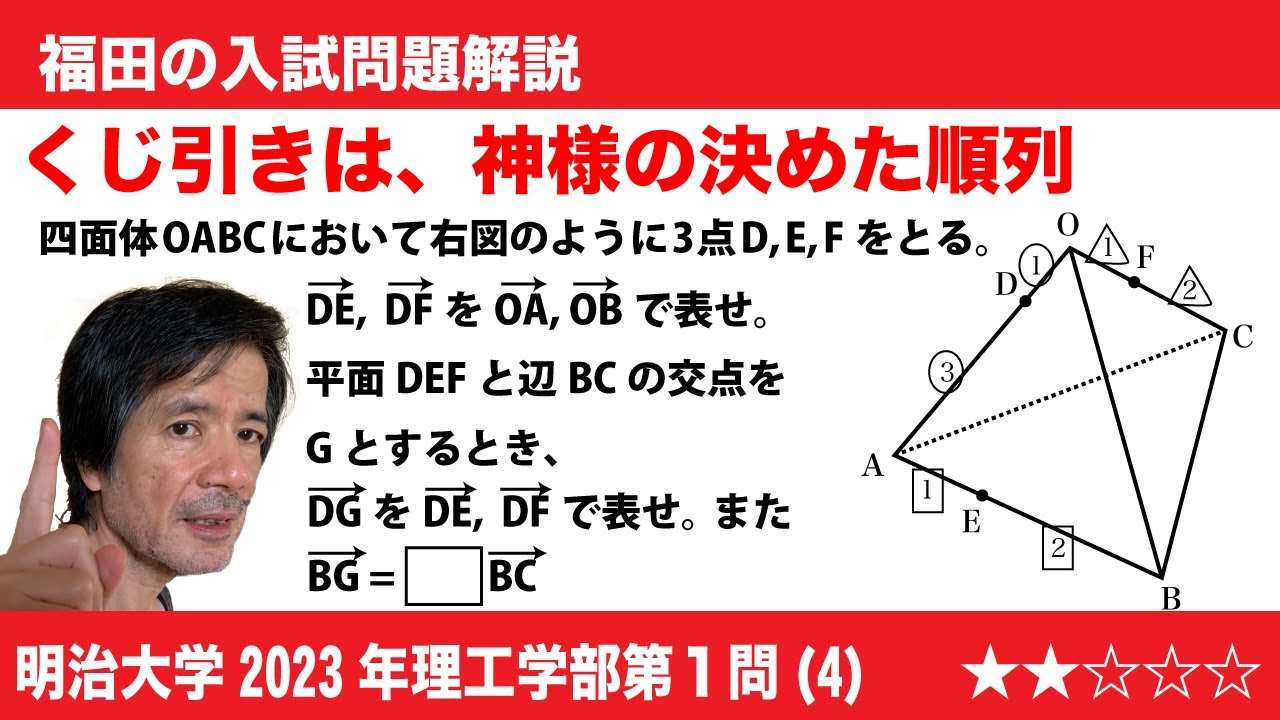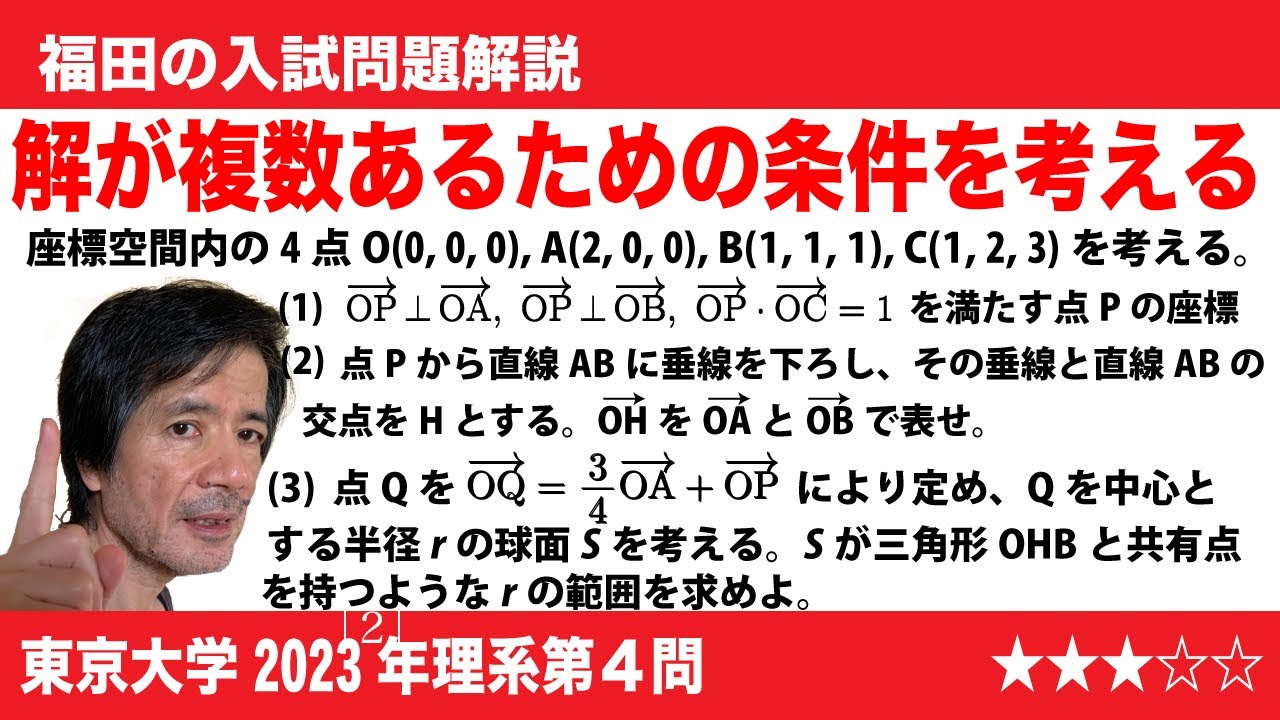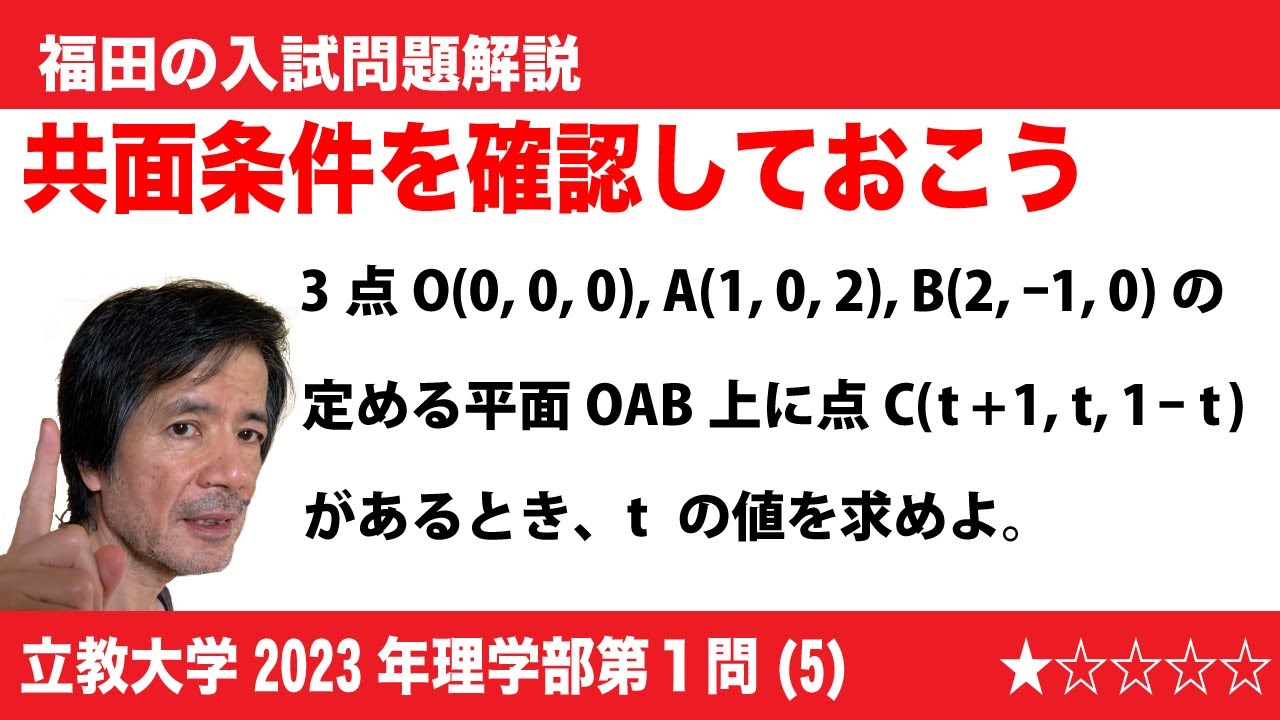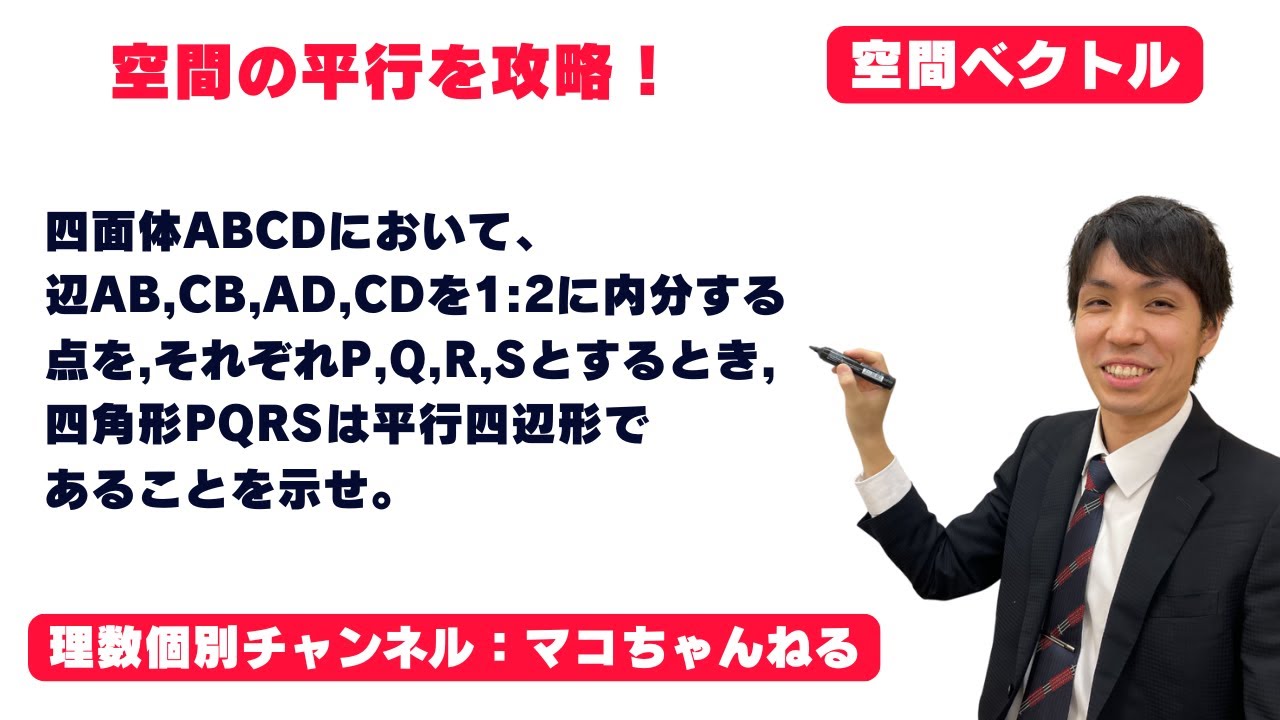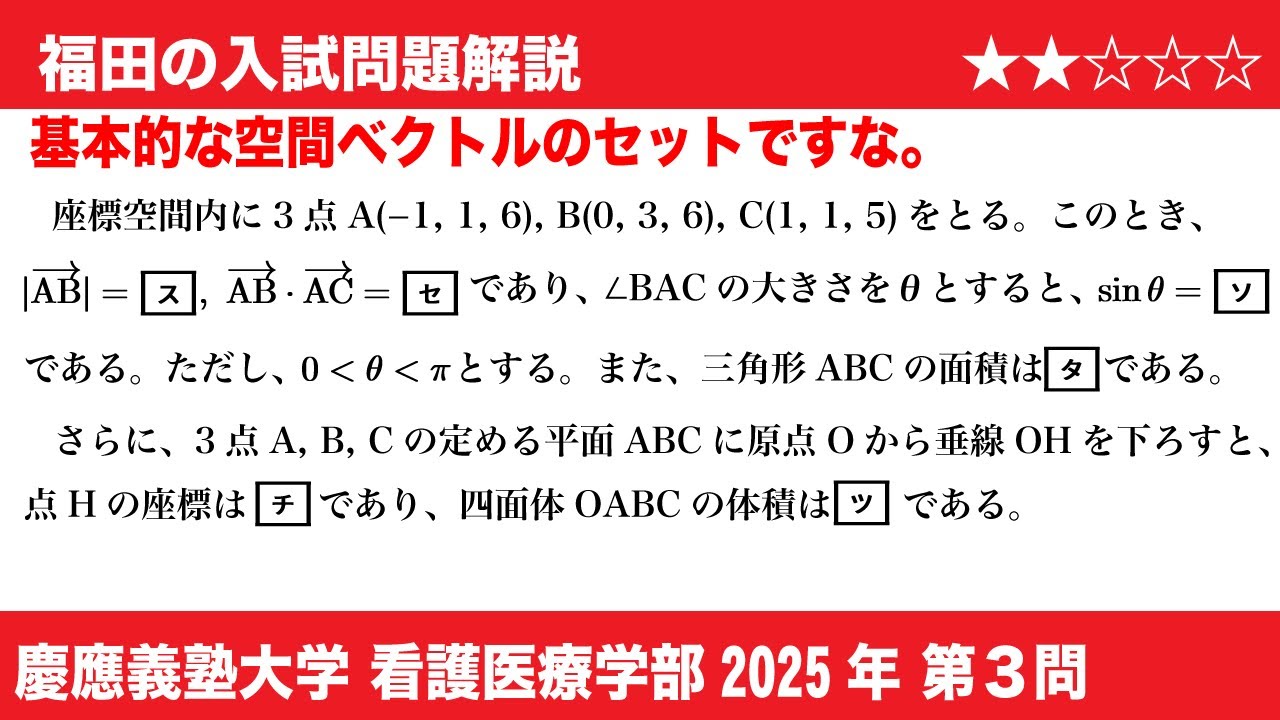問題文全文(内容文):
空間内の4点$O、A、B、C$は同一平面上にないとする。点$D,P,O$を次のように定める。
点$D$は$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{2OB}+\overrightarrow{3OC}$を満 たし、点Pは線分$OA$を1: 2に内分し、点Qは線分$OB$の中点である。
さらに、直線$OD$上の点$R$を $OC$が交点を持つように定める。
このとき、線分$OR$の長さと線分$RD$の長さの比$OR: RD$を求めよ。
2023京都大過去問
空間内の4点$O、A、B、C$は同一平面上にないとする。点$D,P,O$を次のように定める。
点$D$は$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{2OB}+\overrightarrow{3OC}$を満 たし、点Pは線分$OA$を1: 2に内分し、点Qは線分$OB$の中点である。
さらに、直線$OD$上の点$R$を $OC$が交点を持つように定める。
このとき、線分$OR$の長さと線分$RD$の長さの比$OR: RD$を求めよ。
2023京都大過去問
単元:
#大学入試過去問(数学)#空間ベクトル#空間ベクトル#学校別大学入試過去問解説(数学)#京都大学#数学(高校生)#数C
指導講師:
数学・算数の楽しさを思い出した / Ken
問題文全文(内容文):
空間内の4点$O、A、B、C$は同一平面上にないとする。点$D,P,O$を次のように定める。
点$D$は$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{2OB}+\overrightarrow{3OC}$を満 たし、点Pは線分$OA$を1: 2に内分し、点Qは線分$OB$の中点である。
さらに、直線$OD$上の点$R$を $OC$が交点を持つように定める。
このとき、線分$OR$の長さと線分$RD$の長さの比$OR: RD$を求めよ。
2023京都大過去問
空間内の4点$O、A、B、C$は同一平面上にないとする。点$D,P,O$を次のように定める。
点$D$は$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{2OB}+\overrightarrow{3OC}$を満 たし、点Pは線分$OA$を1: 2に内分し、点Qは線分$OB$の中点である。
さらに、直線$OD$上の点$R$を $OC$が交点を持つように定める。
このとき、線分$OR$の長さと線分$RD$の長さの比$OR: RD$を求めよ。
2023京都大過去問
投稿日:2023.03.23