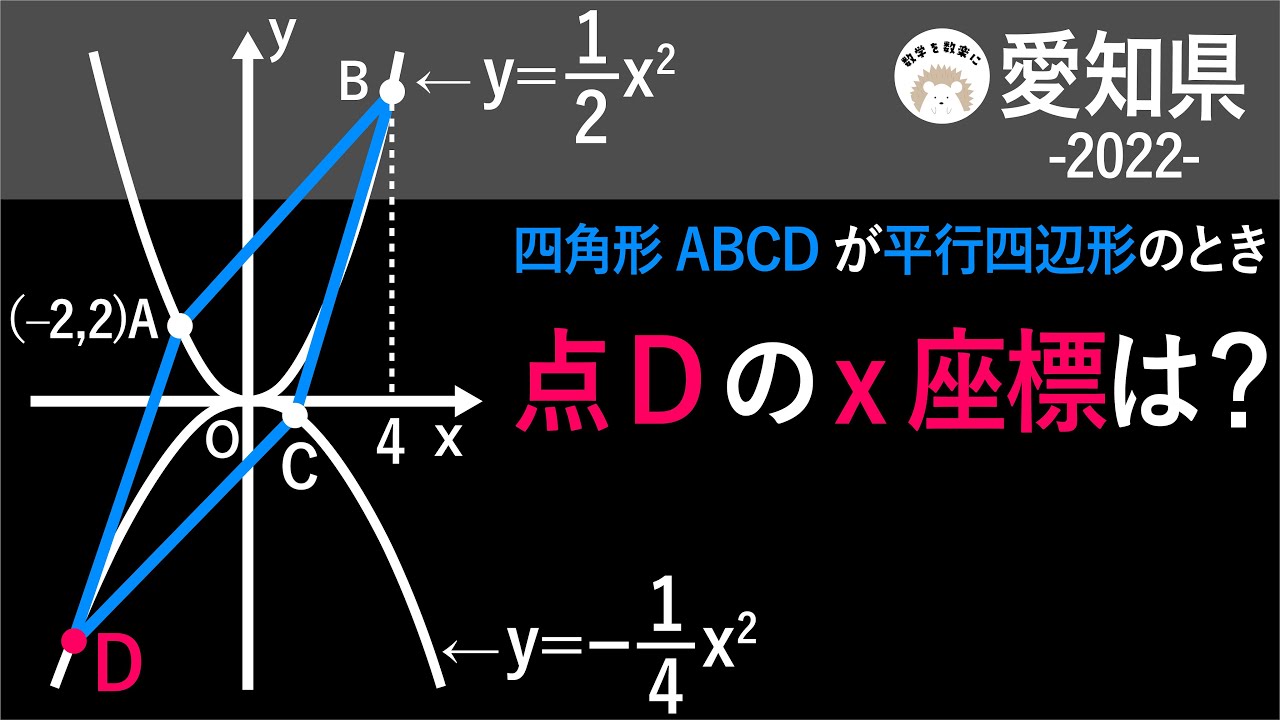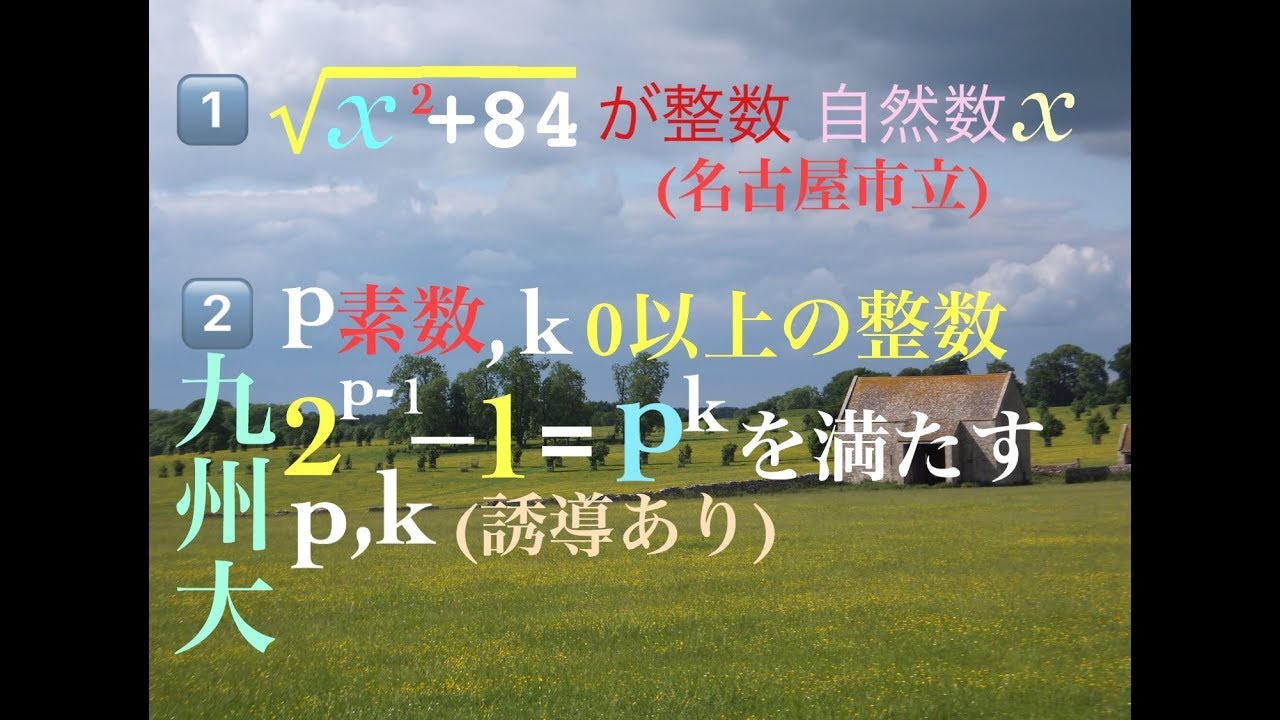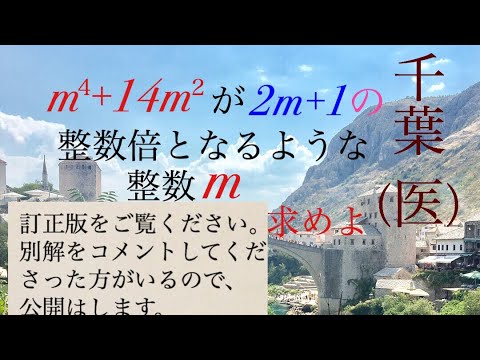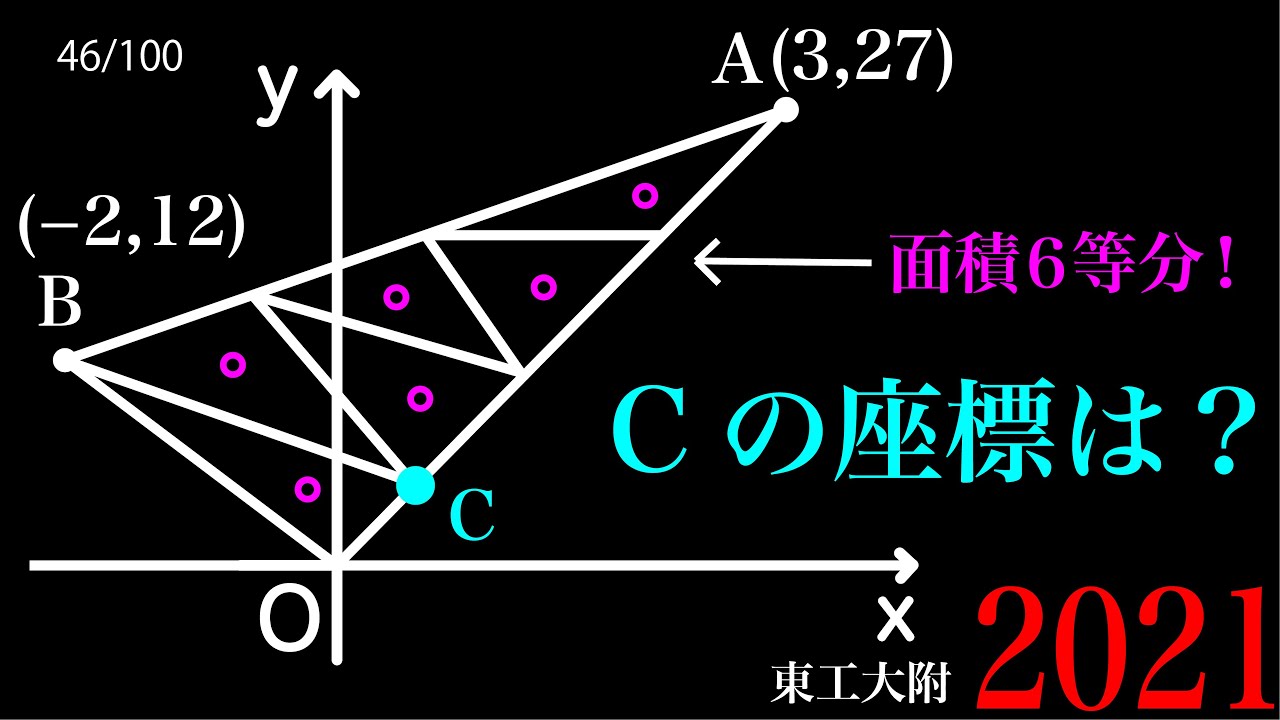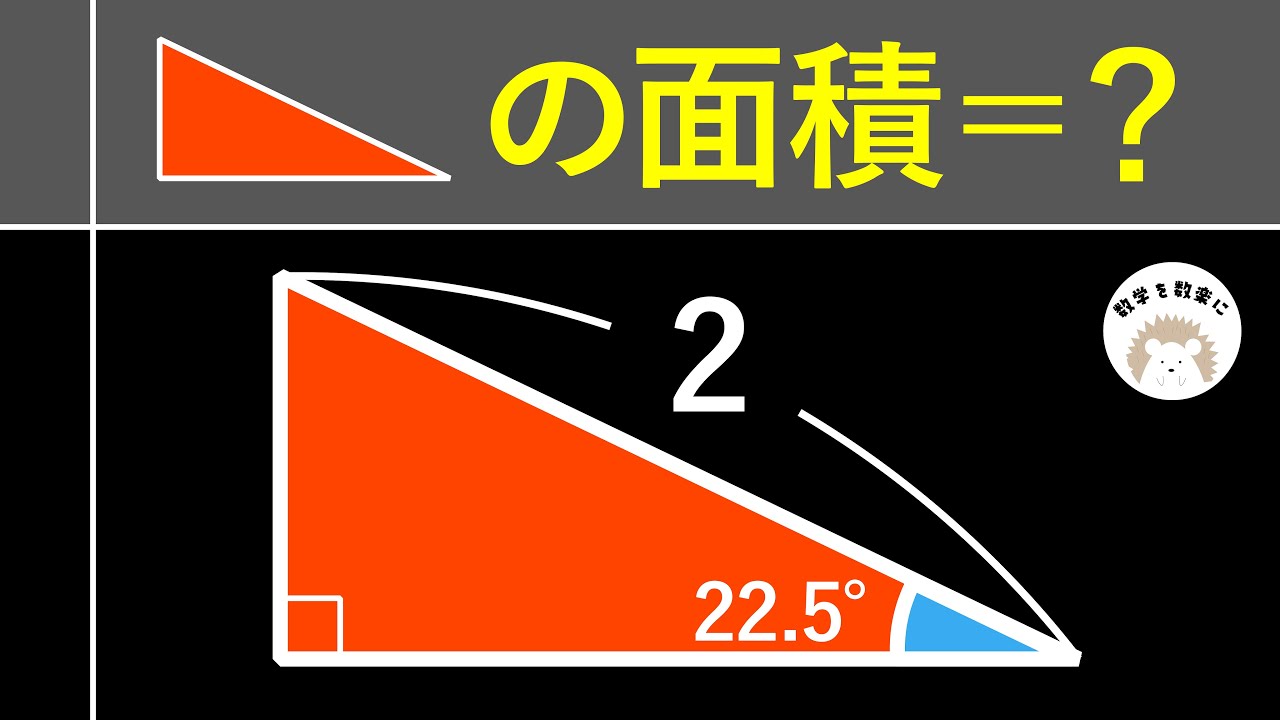問題文全文(内容文):
${\large\boxed{5}}$いま、ADを下底、BCを上底とする台形ABCDにおいて、$\angle BAD=\angle CDA=60°,$
$|\overrightarrow{ AB }|=2,|\overrightarrow{ BC }|=1$となっている。
(1)$|\overrightarrow{ BD }|=\sqrt{\boxed{\ \ アイ\ \ }}$であり、台形ABCDの外接円の半径は$\frac{\sqrt{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}}{\boxed{\ \ オカ\ \ }}$である。
(2)外接円の中心をOとするとき、内積$\overrightarrow{ AB }・\overrightarrow{ AO }=\boxed{\ \ キク\ \ },\overrightarrow{ AD }・\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ ケコ\ \ }}{\boxed{\ \ サシ\ \ }}$である。
(3)$\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ スセ\ \ }}{\boxed{\ \ ソタ\ \ }}\ \overrightarrow{ AB }+\frac{\boxed{\ \ チツ\ \ }}{\boxed{\ \ テト\ \ }}\ \overrightarrow{ AD }$である。
2022慶應義塾大学総合政策学部過去問
${\large\boxed{5}}$いま、ADを下底、BCを上底とする台形ABCDにおいて、$\angle BAD=\angle CDA=60°,$
$|\overrightarrow{ AB }|=2,|\overrightarrow{ BC }|=1$となっている。
(1)$|\overrightarrow{ BD }|=\sqrt{\boxed{\ \ アイ\ \ }}$であり、台形ABCDの外接円の半径は$\frac{\sqrt{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}}{\boxed{\ \ オカ\ \ }}$である。
(2)外接円の中心をOとするとき、内積$\overrightarrow{ AB }・\overrightarrow{ AO }=\boxed{\ \ キク\ \ },\overrightarrow{ AD }・\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ ケコ\ \ }}{\boxed{\ \ サシ\ \ }}$である。
(3)$\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ スセ\ \ }}{\boxed{\ \ ソタ\ \ }}\ \overrightarrow{ AB }+\frac{\boxed{\ \ チツ\ \ }}{\boxed{\ \ テト\ \ }}\ \overrightarrow{ AD }$である。
2022慶應義塾大学総合政策学部過去問
単元:
#数A#大学入試過去問(数学)#図形の性質#周角と円に内接する四角形・円と接線・接弦定理#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)
指導講師:
福田次郎
問題文全文(内容文):
${\large\boxed{5}}$いま、ADを下底、BCを上底とする台形ABCDにおいて、$\angle BAD=\angle CDA=60°,$
$|\overrightarrow{ AB }|=2,|\overrightarrow{ BC }|=1$となっている。
(1)$|\overrightarrow{ BD }|=\sqrt{\boxed{\ \ アイ\ \ }}$であり、台形ABCDの外接円の半径は$\frac{\sqrt{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}}{\boxed{\ \ オカ\ \ }}$である。
(2)外接円の中心をOとするとき、内積$\overrightarrow{ AB }・\overrightarrow{ AO }=\boxed{\ \ キク\ \ },\overrightarrow{ AD }・\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ ケコ\ \ }}{\boxed{\ \ サシ\ \ }}$である。
(3)$\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ スセ\ \ }}{\boxed{\ \ ソタ\ \ }}\ \overrightarrow{ AB }+\frac{\boxed{\ \ チツ\ \ }}{\boxed{\ \ テト\ \ }}\ \overrightarrow{ AD }$である。
2022慶應義塾大学総合政策学部過去問
${\large\boxed{5}}$いま、ADを下底、BCを上底とする台形ABCDにおいて、$\angle BAD=\angle CDA=60°,$
$|\overrightarrow{ AB }|=2,|\overrightarrow{ BC }|=1$となっている。
(1)$|\overrightarrow{ BD }|=\sqrt{\boxed{\ \ アイ\ \ }}$であり、台形ABCDの外接円の半径は$\frac{\sqrt{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}}{\boxed{\ \ オカ\ \ }}$である。
(2)外接円の中心をOとするとき、内積$\overrightarrow{ AB }・\overrightarrow{ AO }=\boxed{\ \ キク\ \ },\overrightarrow{ AD }・\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ ケコ\ \ }}{\boxed{\ \ サシ\ \ }}$である。
(3)$\overrightarrow{ AO }=\frac{\boxed{\ \ スセ\ \ }}{\boxed{\ \ ソタ\ \ }}\ \overrightarrow{ AB }+\frac{\boxed{\ \ チツ\ \ }}{\boxed{\ \ テト\ \ }}\ \overrightarrow{ AD }$である。
2022慶應義塾大学総合政策学部過去問
投稿日:2022.07.06